みなさん、こんにちは。
のりそらです。
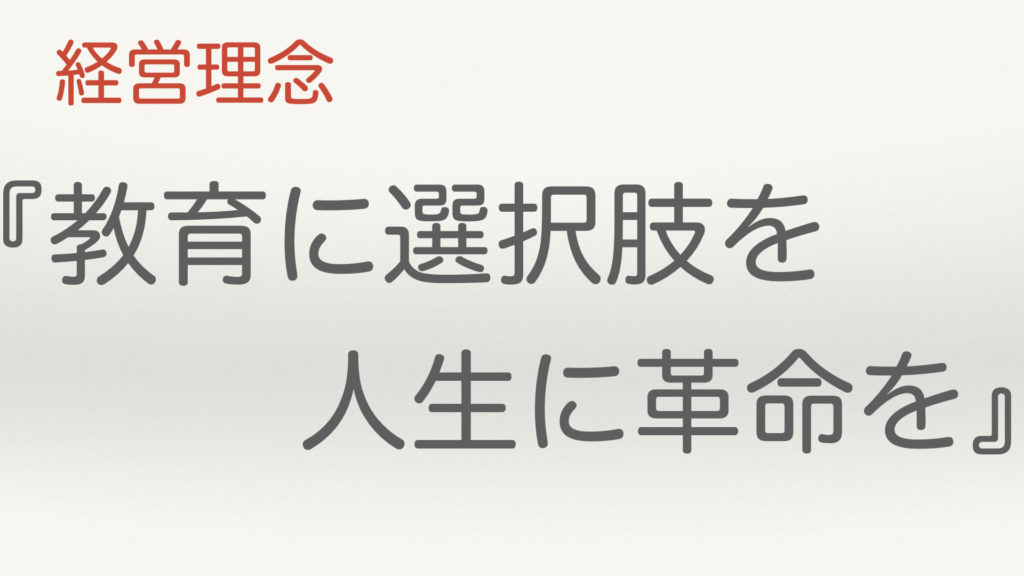
私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。
ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。
さて、今回は、テストや通知表のない小学校についてお話をさせていただきます。
本日の内容:【教えて、のりそら先生】テストや通知表のない小学校開校へ

題して『【教えて、のりそら先生】テストや通知表のない小学校開校へ』といった内容でお届けします。
みなさんは、通知表についてどのように感じていますか?
私は、これまでの、また現在の通知表というものに対しては、疑問をもっています。
その理由は、評価軸が学習に偏っているからです。
もっと言うと、テストの点数に偏っているからです。
もっと子どもたちが自分の現在地を具体的に知り、良い部分は伸ばし、そうでない部分は具体的な改善方法の道標となるようであるべきだと考えています。
私見はこの辺にしておき、ここでは開校が決まっているある小学校の様子についてご紹介することで、通知表について考える機会としていきたいと考えます。
今回このお話を聞くことで、通知表の意味について考えることができます。
お子さんの教育について関心ををおもちの保護者の方々、志をもって子どもたちのために活動しているすべての方々、今何かに一生懸命に挑戦されている方々、教育に関心のあるすべての方々に向けてお話をしていきます。
どうぞお付き合いください。
“テストや通知表のない小学校”開校へ

テストや通知表がなく、児童が好きな授業を選べる。
そんなユニークな私立小学校「まおい学びのさと小学校」が2023年4月に北海道長沼町に開校する見通しとなっています。
体験型学習を中心とした学校設置計画が昨秋の道私立学校審議会で了承されたのです。
計画を提出したNPO法人「まおい学びのさと」の細田孝哉代表理事は、
「子どもたちの好奇心を最大限信頼して、のびのび通える学校をつくりたい」
と意気込んでいるということです。
体験学習をメインに子どもたちの自主性を育む和歌山県橋本市の私立小中学校「きのくに子どもの村学園」がモデルとなっているそう。
「楽しくなければ学校ではない」をモットーに長沼町で盛んな農業やアイヌの楽器づくり、自然体験などの体験授業が半分を占める予定だそうです。
札幌山の手支援学校教諭でもある細田代表理事は、
「例えば、米作りをする中で作付面積を計算したり、気候や流通を学んだりすれば、学習指導要領で定められた算数や理科、社会を学ぶことができる。子どもを学校の中に閉じ込めるのでなく地域にどんどん出て行って、豊かな体験をいっぱいしてもらおうと思っている」
と話しています。
将来的には地元食材を生かした食事も提供する予定だそうです。
校舎は、20年3月に廃校となった旧北長沼小を使用するとのこと。
1学年の定員は20人で、1~4年生の計80人での開校を見込んでいます。
札幌市などニーズのある近隣自治体とのスクールバスを運行する予定だそうです。
4年生の卒業に合わせ、中学校を開設することも計画しているとのことです。
同NPOは、17年に前身の「北海道に自由な小学校をつくる会」が発足しました。
19年の道私立学校審議会にも計画を提出しましたが、資金不足で取り下げ、昨年は児童確保の見込みがないなどの理由で了承されませんでした。
開校初年度の運営資金は寄付などでめどがたち、現時点で約60人の入学希望者がいるといいます。
順位づけは必要なのか?

日本の学校では、多くの分野で順位付けが行われており、勉強やスポーツにおいて自分が何番なのか、常に意識する必要がありました。
偏差値教育に対する批判が高まったことから、最近では明示的に順位を示すことはしなくなりましたが、基本的に入学試験はペーパーテストの点数で決まるので、見えにくいようにしていても、現実に順位付けは存在しています。
こうした順位付けについては、以前から賛否両論となってきました。
過度な順位付けが精神面によくない影響を及ぼすとの考えから、徒競走などでも全員が1番というような扱いをする学校もあるようです。
一方で、競争させなければ子どもは伸びない、社会に出れば常に競争なので、小学校の段階からそれに慣れさせておく必要がある、といった理由で、順位付けを強く望む意見もあります。
社会において競争がなくならないというのは厳然とした事実ですから、むやみに競争を否定したところで、建前論になってしまうというのはその通りでしょう。
しかしながら、昭和の時代と同じように、学校のテストも徒競走も、全員が同じゲームに参加し、1番からビリまで順位を付けるというやり方は、そろそろ時代に合わなくなりつつあります。
時代はすでに変わった

昭和の時代までは、とにかく何でも丸暗記すれば、たいていの問題に対処できました。
ゲームのルールは単純そのものですから、とにかく競わせて頑張らせれば、それなりの成果を得ることができたわけです。
結果として、全員参加の順位付けが標準的になったものと思われます。
しかしデジタル化が進んだ今の時代においては、単純な知識であれば“ググれば”事足ります。
丸暗記していることの価値は、以前と比較して激減したといってよいでしょう。
むしろ、すでに存在している異なる知見を組み合わせたり、見方を変えることによって新しい価値を生み出すなど、いわゆる創造性が重視されるようになってきました。
ビジネスの世界でも、単純にモノの販売数量を競うのではなく、ゲームのルールを変えてしまったり、発想を逆転させるといったやり方で、まったく新しい市場を開拓する方法が注目されています。
このような新しい時代においては、単純なルールで競わせているだけでは、十分な成果を得ることができません。
というよりも、新しい時代は全世界的に競争が激化しており、どのようなルールを作るのかという部分ですら競争環境にさらされているのが現実です。
昭和の時代までは、誰かが作ったルールの中で高得点を取ればそれで事足りたのですが、今の時代においては、他人が作ったルールで競争する段階で「負け」になってしまうのです。
つまり、競争がなくならないどころか、抽象化が進み、さらに複雑になっているというのが現実です。
私は、競争自体を否定するつもりはありませんが、他人が作ったルールを何の疑問もなく受け入れ、その中で点数を競うという昭和的な競争の発想は、そろそろ捨て去るべきだと思います。
これからの時代は・・

先ほど競争がより複雑化し、激しくなっているという話をしましたが、一方で、社会のデジタル化が進んだことによって、一定のスキルさえ身につければ、長時間労働をしなくても相応の業務をこなせるようになってきました。
独創性などより高い次元での成果を求める人は、自ら志願して激しい競争社会に身を投じればよいでしょうし、そうした競争を好まない人は、淡々と業務をこなし、私生活を大事にする生き方の方が幸福感を感じやすいと思います。
誰がどのような能力を発揮できるのか、先を読むのが難しい時代ですから、最初からゲームのルールを絶対視せず、いろいろなことにチャレンジさせる方向性を目指した方が、社会全体として得られる富は大きくなるでしょう。
ある仕事に対して、募集する人数よりも応募者の数が多ければ、そこで競争が発生するのは仕方のないことです。
しかしながら、仕事に対して賃金が支払われる、いわゆるジョブ型の雇用が一般的になれば、その仕事に従事するために必要となるスキル(あるいは学歴)は事前に明示されます。
その仕事に就きたいと考える人は、必要な学歴を得ていけばよいという発想になりますから、最初から同じゲームで全員が競争する社会とは違った価値観になっていくはずです。
諸外国では、現時点における個人の能力を見極めた上で、全体で何番なのかではなく、努力によってどれだけ能力が高まったのかを重視する教育方法が主流となりつつあります。
体育についても、それぞれの運動能力に合わせて基準を設定し、どのくらい体力が向上したのかで評価が行われます。
何をするにも基礎学力は重要ですが、基礎学力を高めるためのインセンティブが、他人との相対的な位置関係だけで決まるわけではありません。
自分で目標を設定し、その目標をどう乗り越えさせるのか児童生徒に考えさせた方が、新しい時代における人材育成としては、よりふさわしいのではないでしょうか。
まとめ

さて、今回は、「【教えて、のりそら先生】テストや通知表のない小学校開校へ」というお話をさせていただきました。
時代が変われば、学校が変わるのも当然でなければなりません。
もっと厳密に言うならば、学校の仕組みや形態やシステムやカリキュラムや教員の指導力や保護者との関わりなど、あげればキリがありません。
これらが、依然として全時代的過ぎて、しばらく前から時代にそぐわないものになっていると思います。
よって、この「まおい学びのさと小学校」の行く末は、期待感をもって見守っていきたいと考えています。
私のりそら、日本の、世界の学校の未来がより良いものとなるようこれからも発信していきます。
加えて、これまでのように先生方の日頃の頑張りを世の中に伝えていきたいと思います。
先生方は、どうか日本の子どもたちのために、目の前の子どもたちのために、真っ直ぐにエネルギーをお使いください。
私のできることはさせていただきます!!
のりそらからは以上です!!
もしこの記事がお役に立てたら下の2つのバナーを1日1回ポチッとクリックお願いいたします!!
それを活力に頑張ります↓↓
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
メルマガもやってます。
リンクを貼っておきます↓↓
そして、これ、便利です。疲れたらドラマでも観て一息つきましょう↓↓


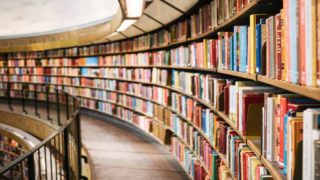



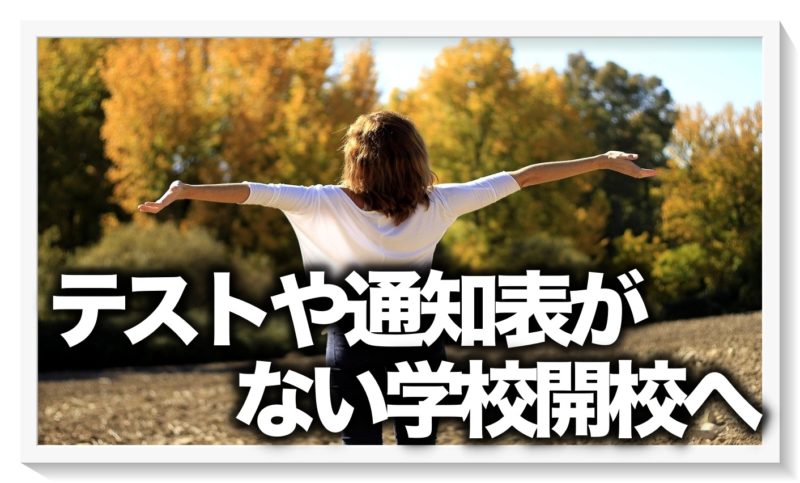




コメント