みなさん、こんにちは。
のりそらです。
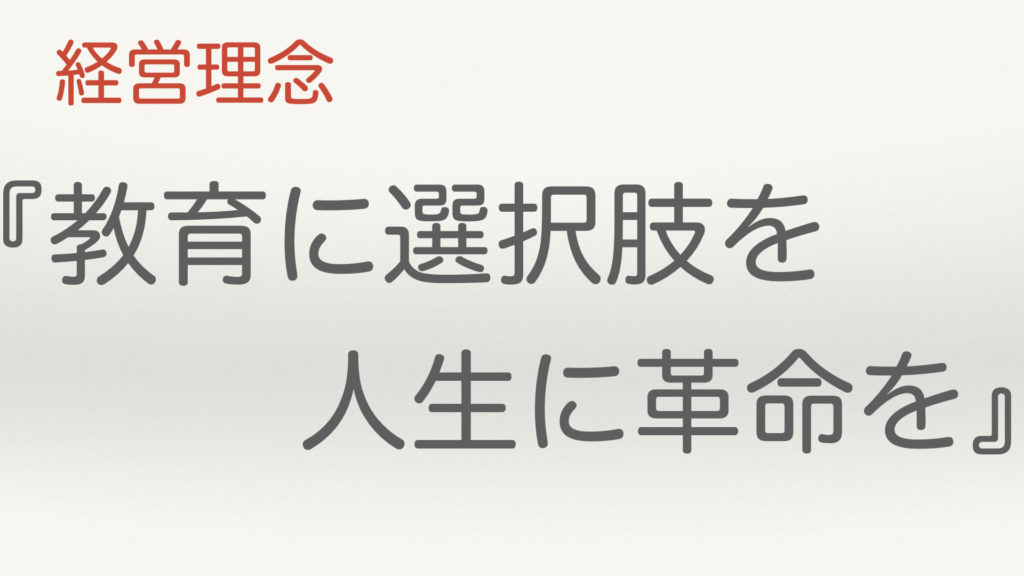
私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。
ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。
さて、今回は、お子さんにできるある質問についてお話をさせていただきます。
本日の内容: 【教えて、のりそら先生】「成績上がる子」見抜くただ1つの質問

題して『【教えて、のりそら先生】「成績上がる子」見抜くただ1つの質問』といった内容でお届けします。
先日東洋経済オンライン(https://toyokeizai.net/)の記事に興味深いものを見つけました。
タイトルは、『東大生直伝「成績上がる子」見抜くただ1つの質問』です。
ここでの内容の一部を紹介させていただき、どうしたら「成績上がる子」になるのか、一緒に考えていきましょう。
今回このお話を聞くことで、お子さんが「成績上がる子」なのかを見抜くことができます。
お子さんの教育について関心ををおもちの保護者の方々、志をもって子どもたちのために活動しているすべての方々、今何かに一生懸命に挑戦されている方々、教育に関心のあるすべての方々に向けてお話をしていきます。
成績が上がる子とそうでない子の違い

成績が上がる子とそうでない子を見極める質問というのがあります。
それは、
「今日はこれから、どんな勉強をする?」
というものです。
これに対する回答というのは、3種類に分類できます。
A:「英語をやります!」と科目を教えてくれるタイプ
B:「数学の参考書を進めているので、それを3問終わらせます!」と勉強量を教えてくれるタイプ
C:「英単語帳を覚えるために、英単語帳の1~100番を覚えます!」と勉強の中身を教えてくれるタイプ
このうち、成績が上がりやすいのは圧倒的に「C」のタイプです。
Aのタイプは、自分が何を頑張っているのかを教えてくれているわけですが、それの結果どうなるのかがあまり想像できていません。
だから、「英語の何をやるの?」と聞くと、「え?うーん」と考えこんでしまいます。
Bのタイプは一見成績が上がりそうですが、「2問やった」「4ページ終わらせた」というのは「量」をこなすことが目的になってしまいがちです。
「この一冊を頑張れば合格できるはずだ!」と考えて、こなすこと自体が目的になってしまいがちなのです。
「目的」が明確であることの重要性

逆にCのタイプは、「目的」が明確な場合が多いです。
「英単語を覚える」という目的が先に来ていて、そのために勉強がひもづいています。
AもBも、頑張った先に何があるのかを想像できていません。
それだと、ただがむしゃらに何かをやっているだけとなります。
でも、Cは、目的のために努力をしています。
こういうタイプは、きちんと結果につながる努力をすることができるのです。
「頑張る」のは、あくまで手段

「頑張る」のは、あくまでも手段でしかありません。
重要なのは、「なぜ頑張るのか」という目的を考えること。
「頑張る」が手段になっているうちは、結果にはつながらないのです。
「目的が先行して努力を積み上げていく」という意識を持つということにほかなりません。
「頑張る思考」が強い勉強法を実践している人は、時間ばかりを掛けてしまって結果が出ないということもあります。
そうではなく、しっかりどう勉強を効率的にやっていくのか自分の中でしっかり考えていくことができる人でないと、勉強がはかどらないのです。
「頑張る」が生む大きなミス

「頑張る」というのは、場合によって大きなミスを誘発させてしまいます。
それは「もっと頑張ってしまう」ということです。
世の中には、PDCAサイクルというものが存在します。
仕事の効率を上げるための考え方で、
「Plan(計画)を立て、Do(実行)して、それをCheck(確認)したうえでAction(改善)してみる」
というサイクルを徹底することで、次に活かしていく、というものです。
勉強もこれと同じように、計画を立て、それを実行し、それをまた振り返っていく思考が必要になって来るタイミングというのがあります。
そして、このサイクルで一番大切なのは「Check」です。
自分の勉強の中で効率が悪い部分や意味がないものをどんどん削っていく姿勢を持たなければならず、うまくいかなかったポイントからそれを学ばなければなりません。
しかし、このCheckで頑張ってしまっている人は、内容について考えず、漠然と「もっと頑張らないと」という間違ったCheckをしてしまうことが多いです。
「精神論に逃げる勉強」は意味がない

確かに頑張れば少しは結果が出るかもしれませんが、そういうことではなく、もっと考えて、もっと結果につながるような思考をしなければ、勉強はどんどん無駄なものになっていき、PとDだけを永遠と繰り返してしまうことになるわけです。
しっかりと合理的に判断していく必要があるために、この「頑張る勉強」「精神論に逃げる勉強」には本質的な意味がないのです。
大切なのは、「明確な目的のある努力」、つまり「目的思考の努力」です。
その努力を経て、どういう状態になるのが理想なのか、を考える努力をすることが重要なのです。
数学の問題集を解くのはいいけれど、それで一体どういう状態になるのが理想なのかを考える。
問題が全部できるようになるのが目的なのか、詰めが甘い部分を矯正するのが目的なのか、またはざっと復習するのが目的なのか、全然違いますよね。
がむしゃらに勉強を頑張るのではなく、具体的に、何を目的にしているのかを考えた努力を積み上げていくことを心がけると、結果につながっていくのです。
いかがでしょうか?
目的をしっかりともつということをぜひ、実践していただければと思います。
勉強に目的をもたせるには・・

「勉強に目的意識をもちなさい」
いうのは簡単ですが、子どもに実践させるのは難しいものです。
何事にも同じことが言えますが、ある事柄を子どもたちが理解し、納得し、習慣化していくには、成功体験が必要です。
簡単に成功体験が得られるようなものであれば良いですが、こと勉強については、成功体験を得るまでに若干の時間がかかります。
それゆえ、成功体験を得るまで、繰り返し繰り返しその必要性と意義を確認しながら一定の回数、一定の時間継続する必要があります。
”勉強に目的意識をもつ”
当たり前に重要なことですが、これをきちんとできている子どもは残念ながら実に少ないように思います。
成功体験を得るまで、繰り返し繰り返しその必要性と意義を確認しながら一定の回数、一定の時間継続するということが徹底できていない証拠のように思います。
根気強さは、物事を習慣化する上では非常に重要な役割を果たすと考えます。
まとめ

さて、今回は、「【教えて、のりそら先生】「成績上がる子」見抜くただ1つの質問」というお話をさせていただきました。
記憶力や論理的思考力・説明力や抽象的な思考能力など、「頭がよい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があり、後天的に獲得している能力は少ないと考える人が多いのではないでしょうか。
実は、そんなことはありません。
目的意識をもてる人に育てていけば良いのです。
私たちNEXTAGE SCHOOLの信念は、そこにあります。
私のりそら、日本の、世界の学校の未来がより良いものとなるようこれからも発信していきます。
加えて、これまでのように先生方の日頃の頑張りを世の中に伝えていきたいと思います。
先生方は、どうか日本の子どもたちのために、目の前の子どもたちのために、真っ直ぐにエネルギーをお使いください。
私のできることはさせていただきます!!
のりそらからは以上です!!
もしこの記事がお役に立てたら下の2つのバナーを1日1回ポチッとクリックお願いいたします!!
それを活力に頑張ります↓↓
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
メルマガもやってます。
リンクを貼っておきます↓↓
そして、これ、便利です。疲れたらドラマでも観て一息つきましょう↓↓


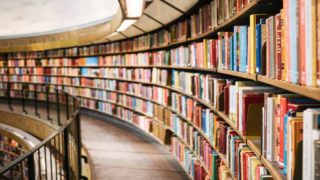



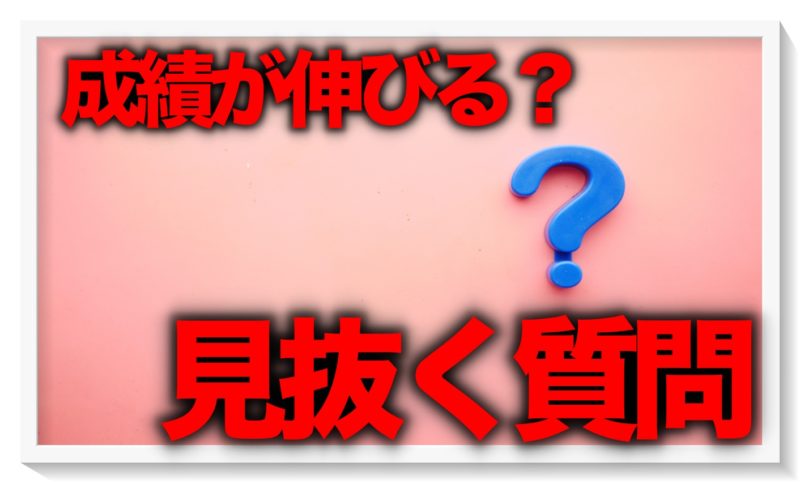

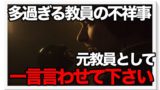


コメント
[…] […]