みなさん、こんにちは。
のりそらです。
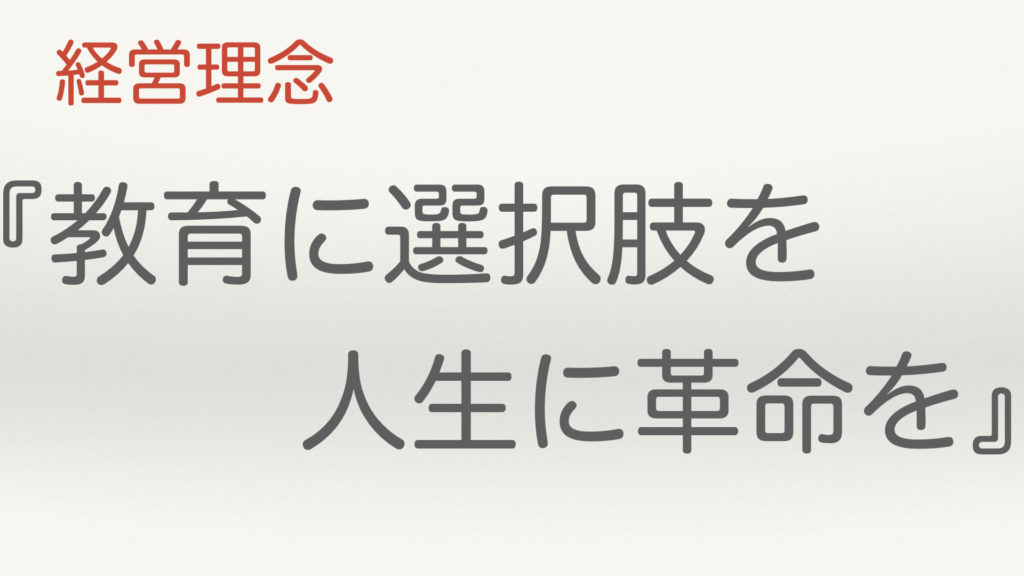
私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。
ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。

さて、それでは『教師インターン』第8講目やっていきたいと思います。
前回は、『子どもの褒め方、叱り方』ということでみなさんが現場に出て、早速実践するであろう内容についてお話をさせていただきました。
そして、今回ですが、学習についての話をしようと思います。
子どもたちにとって、学校における本分は”勉強をすることです。
これは教師にとっても同様のことが言え、授業をするということは教師の本分であると言えます。
教師にとって本分であるにもかかわらず、実際に勤務を開始してみると、授業の準備、『教材研究』,
これに充てる時間というのが驚くほど少ないということがわかります。
教材研究以外の仕事に忙殺されてしまって、ついつい教材研究が後回しになってしまうのです。
しかし、授業は毎日毎日複数時間やってくる。
万全な準備をしなくてこなせるのか?と不安になりますよね。
では、そのような状況で、経験のある先生方はどのように授業をしているか?
その答えは、ポイントをつかんで授業をしているといった感じです。
加えて、ある程度教科によって自分の型のようなものを持っている場合がほとんどです。
ポイントをつかんだ授業、自分なりの型というのは、経験によって身につきます。
よって、それほど心配はしていません。
ここでお伝えしたいのは、小学校における基礎学力とされる国語と算数という教科への理解です。
この2教科についての識見を深めることで、良い授業へと成長させていくことができると感じたので、今回国語と算数について取り扱うことにしました。
具体的な授業の進め方などは、学校で配られる”指導書”というものに詳しく書いてありますので、そちらを参照すれば大丈夫です。
というわけで、第8講目の今回の内容は、
今回の内容:【教師インターン第8講】基礎学力(国・算)をつけるために

『基礎学力(国算)をつけるために』という内容でお話ししていきたいと思います。
同様の内容を動画でもご覧いただけます↓↓
本題に入る前に、一つご紹介したいお話があります。

『国語の読解力って、どうしたらつくようになりますか?』と聞かれたら、あなたはどう答えますか?
『えっ、そんな急に言われても・・』となりますよね。
しかし、実際には、4月の授業参観の後の懇談会で保護者に聞かれるかもしれません。
もっと可能性が高いのは、家庭訪問がある場合です。
家庭訪問では、一人ひとりの学習や生活の状況についてお話しするわけですが、その際に”学習面での課題”として多くの子が持ちがちで、親もなんとかしたいと思っていがちなのが、”国語の読解力”なんです。
こういう質問に対する答えは、普段から考える機会を持っていなければ、なかなかうまく答えることができません。
そして、もし、わからなくても『わかりません』とは、とても言いづらい内容ですよね。
だって『この先生大丈夫か?』と不審に繋がってしまいますもんね。
だから、ここで一回ちゃんと学んでおきましょう。
国語力

まずは、『国語力』についてお話しさせていただきます。
みなさんは、自分に『国語力』があると思いますか?
「学力向上の鍵は『国語力』向上にある」とは、多くの教育者がそろって唱えることです。
理系教科を学ぶにしても、その内容を理解するためには教科書や参考書を読まなければなりません。
人間が言葉を使って物事を考え理解することを思えば、その主張ももっともだと言えるでしょう。
では、『国語力』をどう定義すれば良いでしょうか?
学校では、「読む」「聞く」「書く」「話す」の4分野を評価の対象としておりますが、ここでは、わかりやすくするため、”インプットのための「読解力」と、アウトプットのための「表現力」の2つを指すことにします。
国語力① 読解力

まずは、『読解力』についてです。
とりわけ読解力は、すべての勉強における最重要要素だと考えられています。
そのため、よく保護者からの質問にも上がるというわけですね。
では、なぜ、読解力があるとよいのでしょうか?
その理由は、読解力があると、文章を読んだときに、「書いた人は何が言いたいのか」「何を問われているのか」を明確につかめるからです。
「読解力がない」と悩む人もいます。
でも、読解力を上げることは決して難しいことではなく、その方法は次の2つに尽きます。
読解力① 丁寧に読む

まずは、”丁寧に読む”です。
コツは、本当にこれだけです。
読解力が低い人は、自分でも気づかないうちに文章を読み飛ばしていたり、自分の思い込みで意味を補ったりしてしまい、解答が著者の意図と離れていくことがとても多いのです。
だから、丁寧に読むことが大切なのです。
”丁寧に読む”ためには、訓練が必要です。
活字慣れするように文章に触れることが重要です。
そのためには、実は小学校に上がるよりも前から読書に親しんでいる必要があります。
お母さんがよく読み聞かせをしてくれたお子さんは、”丁寧に読む”ことが出来やすい傾向にありますし、幼い頃から自分で本を読む習慣がある子は、”丁寧に読む”ことが出来ます。
では、小学生になった今からでは遅いのか?といったらそうでもありません。
十分に可能です。
ただ、その頃には読書以上に楽しいことがありすぎて、読書に抵抗感を示してしまう子が多いというのがあります。
これが実は大きなネックになります。
ですから、できるだけ早い段階で読書の楽しさを感じる経験が持てると良いですね。
学校では、”音読”これを宿題として毎日出している先生も少なくないと思います。
私もそうでした。
きちんと毎日その宿題をこなすことでも十分に力が付くと考えて宿題にしますが、取り組みの状況はどうでしょう?
きっといい加減になりがちな宿題になってしまってもいます。
いずれにせよ、国語の授業でより多く”丁寧に読む”機会を設けるなど工夫が必要です。
さて、”丁寧に読む”これは本当に重要なことなのですが、別視点から「読解力」を育む方法を1つご紹介します。
読解力② 体験する

それは、”体験する”ということです。
これはどういうことかというと、人は文章と出会った時に(会話でも同じだと思いますが)難しくて意味がわからないと感じた時に、それについて苦手意識をもつものです。
では、どういったものに難しさを感じるのかというと、自分の生活とかけ離れたまだ見ぬ世界の出来事、これに関しては難しさを抱きます。
もっというと、興味を示さないが故に難しさを感じると言ってもいいかもしれません。
例をあげましょう。
小学生に『子育て本』を読ませてみると、恐らく、理解度は低いです。
しかし、子育て中のママが同じ『子育て本』を読んだら、理解度は高いと思います。
逆にママさんに、『最新ゲームの攻略本』を読んでもらってもさっぱり意味がわからないけれど、小学生にはよく理解できる。
そんなことはありませんか?
この違いに、ヒントがあると思うのです。
そう、それは経験している、もっと深くは『体験している』事柄については、興味も多少はあるので、理解が深くなるということです。
と、いうことは、多くの体験をしている人は、興味のある、理解しやすい文章と出会う確率が高いと言えます。
よって、体験することは、「読解力」につながっていると言えます。
日常の中でなるべく多くの生活経験、体験をさせることが実は、「読解力」につながります。
これは、一つ目の”丁寧に読む”以上に保護者の『なるほど』を引き出せる内容ですよね。
もし、保護者の方に問われたら、ぜひ、こういった話もしてみてください。信頼がアップしますよ。
国語力② 表現力

続いては、『表現力』についてです。
人間は、様々な形で表現をしています。
体を使った身体表現、言葉を使った言語表現などがありますね。
ここでは、言葉を使った言語表現にスポットを当てます。
言語表現には、さらに口語表現と文章表現に分けられます。
特に「国語力」と関連づけられやすいのは、文章表現ですよね。
いわゆる作文とか感想文とか。
口語表現と文章表現というのは、かなり相関性があって、喋れる子は書けるし、書ける子は喋れるということです。
この両方が苦手な子は、頭や心で気持ちを抱いたり、興味を示したりする力が弱いと言えます。
一方、お喋りな子は、頭や心でいろいろなことを考え、いろいろなことを伝えています。
情報を生み出しているんですね。
これがまさにアウトプットです。
では、どうしたら進んでアウトプットをする子になるか?
表現力① 話を聞く

これは、まず、『話を聞く』ことだと思います。
幼い子って比較的お喋りですよね?
そのお喋りが過ぎると、付き合うのが大変で簡単に聞き流してしまったり、時には「うるさい」と叱ってしまったり。
でも、子どもはここで一生懸命口語表現力を磨いている訳です。
この力があれば、その言葉を文字に書き起こすだけで、文章表現力に繋がります。
作文のルールなどは、後からいくらでも鍛えることができます。
しかし、自分の思いを表現することは、その子にしかできません。
だから、子どもがたくさん話したくなる雰囲気づくりをしてあげてください。
学校でも同じです。
子どもたちが話したくなる雰囲気を作るのです。
それは、授業中にも、授業外にも。
そして、その話したことを誰かがきちんと聞いてくれるという状況をつくることも同時に必要です。
しっかりと聞いてもらえた経験を通して、さらに表現をしようと試みるものです。
すると、『表現力』は確実にアップしますよ。
表現力② アウトプットの場を用意する

続いて、表現力をつけるための方法2つ目は、『アウトプットの場を用意する』ことだと思います。
学校でいうと、みんなの前で発表する機会なんかがそれにあたります。
”みんなの前で”ほどおおげさなものでなくても、多くの友達とコミュニケーションをとる機会だったり、ちょっと変化をつけるとすれば、家庭で親戚のおじさんたちとコミュニケートしてみたり、いつもと違う場で、いつもと違う人とコミュニケートすることがアウトプットの場となります。
その程度でも十分だと思います。
よく、親はよく喋るのに、子どもは寡黙、なんていうケースを目にしませんか?
あれなんかは、まさに親が先回りして子どもの代わりにあーだ、こーだと子どもの言いたいことを話してしまうから、子どもの話す機会を奪ってしまっているから、子どもが寡黙になってしまうのでしょうね。
意外というより必然です。気をつけたいですね。
国語力まとめ

さて、ここまでは、『国語力』についてお話ししてきました。
特に、『読解力』に課題をもつお子さんはやはり実に多いです。
体験をさせるという新たな視点でのお話もさせてもらいました。
いろいろなものを見て、いろいろなことを感じることが『読解力』につながります。
ぜひ、学校でもこの辺も意識しながら生活及び授業の計画を立てるようにしてみてください。
『国語力』についてでした。
算数

続いて、『算数』についてお話しさせていただきます。
国語では、『国語力』とよく言いますが、算数は、なぜかあまり『算数力』という言い方をしませんね。
どちらかというと、『計算力』?
でも、計算力は、算数の力の一部に過ぎないですよね。
なんて、前置きが長くなりましたが、『算数』についてです。
算数についても、課題は多くありますね。
例えば、好き嫌い、苦手得意が極端に別れるということがありますね。
小学校程度の算数の力は全員につけて欲しいので、こうあっては困るのですが、実際にはそうなってしまっていますよね。
特に、算数で出来不出来が分かれるのが”思考力”についてです。
わかりやすく言えば、文章題のような問題です。
単純な計算は多くの子がクリアできるのですが、文章題になると途端に難しさを感じてしまう。
そこで、ここでは、”思考力”にスポットをあてて3つポイントをお話をしていきます。
思考力① 基礎の定着

思考力を高めるためにまず必要なことは、『基礎の確実な定着』です。
昔の授業と違って、今の授業では、公式を導き出すまでの過程から子どもたちと考えるような教科書の構成になっています。
早速ですが、ここが大事なポイントです。
この公式を導き出す過程にこそ、思考力のポイントがあります。
過程とは、なぜ、そのようになるのか?という部分ですよね。
ここを論理的にきちんと整理できれば、思考力があると言えるでしょう。
授業者も子どもたちもどうしても結論を急いでしまう傾向にあります。
しかし、過程をじっくりと考えさせる授業を展開し、きちんと基礎が定着するように心がけてください。
思考力② インプット

2つ目は、インプットです。
論理的に過程を考え、過程をインプットします。
そして、その身につけた力を使って、実際に問題演習をします。
実際に手を動かして、頭を働かせながら、より多くの問題を解き、インプットしていきます。『くり返し計算ドリル』というものがあります。
繰り返してやり方を完全にインプットしていくことが算数では大事になってきます。
2つ目は、インプットでした。
思考力③ アウトプット

3つ目は、アウトプットです。
これはあまりきちんと取り組んでいる先生が多くありませんが、すごく大事なことです。
オススメなのは、子ども同士の”教え合い”です。
”教え合い”をする時間を授業の中で設定することです。
例えば、公式につながる過程を考える場面では、グループ活動を取り入れて考えを友達に伝える場をつくることが出来ます。
また、問題演習をする場面でも、出来た人から手を挙げさせ、その子の答えを教師は見に行き丸つけ、丸をもらった子は、ミニ先生となって教室の中を自由に動き回り、丸つけをし、わからない子に教えるという仕組みをつくる。
このようにして、アウトプットをする機会を設けることで、より深く考えるようになり、思考力が身に付くことになります。
思考力だけでなく、当然表現力も身につきますので、ぜひ授業で”教え合い”を取り入れてみてください。
番外編:プログラミング

番外編として『プログラミング』について触れておきます。
『プログラミング』は、2020年から小学校で必修化されました。
そして2021年中学校が後に続きます。
さらに翌年の2022年には、高校で『情報Ⅰ』が必修化され、さらにその先の大学入試共通テストでも出題されることになっています。
そんなプログラミングですが、算数の論理的思考を身につける上での効果が大きく期待されています。
プログラミングとは、簡単にいうと「コンピュータにさせる処理を、順番に書き出したもの」です。
コンピュータは自分で考えることができません。
そのため、コンピュータ自身が自分で考えて行動することはできません。
しかし、人間が指令を出してあげることによって、次のページを表示したり、画像を表示したり、音楽を流したり‥さまざまなことができるようになります。
こういったことをコンピュータ相手に行うのが「プログラミング」です。
人間であれば、なんとなく予想して「次はこうすればいいのかな」と動くことができますが、コンピュータには想像する力がありません。
一連の動きを厳密に、コンピュータにも読み取れる形で命令する(=プログラムする)必要があるのです。
こういった活動を通して、物事を順番に処理していく力が身についていくとされています。
まさに算数の”論理的思考”ですね。
算数まとめ

さて、ここまでは、『算数』についてお話ししてきました。
特に、『思考力』に課題をもつお子さんはやはり実に多いです。
これまで話を聞いていただいてお分かりの通り、『思考力』は算数の中でも高次な力です。
よく算数は積み重ねが大事な教科と言われます。
これまで学んだことがしっかりと身についていなければ、これから学習することを身につけるのが難しくなります。
同様に、基礎がしっかりと身についていなければ、『思考力』は育ち辛くなります。
よって、一朝一夕には力がつかないものなので、コツコツ積み上げていけるように、丁寧に子どもたちの様子を見取ってあげてください。
まとめ

さて、第8講目の今回は、『【教師インターン第8講】基礎学力(国・算)をつけるために』という内容でお話させていただきました。
義務教育段階での学習は、どの子にも確実に定着させたいものです。
それには、子どもたちが前のめりになって学習に臨めるように、工夫した授業を展開することが大切です。
最初はなかなかうまくいきません。
しかし、仮に授業を教えるテクニックは乏しかったとしても、子どもたちに学力を付けることはできます。
それは、熱をもって何度も何度もわかるようになるまで教えることです。
授業に完全なる正解はありません。
ということは、教え方にも完全な正解があるわけではありません。
教科の特性をきちんとした理解した上でどんどんどんどん良い教え方をアップデートして行けるようにしてください。
教育公務員は、その職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければなりませんからね。本日も長い講義となりました。
お疲れ様でした!!
最後までご清聴いただきありがとうございました。
以上で教師インターン第8回目の講義を終わりにします。
お疲れ様でした!!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
この『教師インターン』シリーズをさらに充実した内容でオンラインスクールにて動画販売しています。効率良く学びたい方は、ぜひ一度アクセスしてみてください↓↓
のりそらからは以上です!!
もしこの記事がお役に立てたら下の2つのバナーを1日1回ポチッとクリックお願いいたします!!
それを活力に頑張ります↓↓
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
メルマガもやってます。
リンクを貼っておきます↓↓
そして、これ、便利です。疲れたらドラマでも観て一息つきましょう↓↓

効率よく勉強したい方は、Amazon Audibleがオススメです↓↓
Amazon Audible(オーディブル)無料体験あり

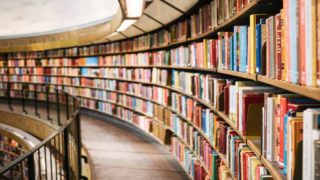








コメント