みなさん、こんにちは。
のりそらです。
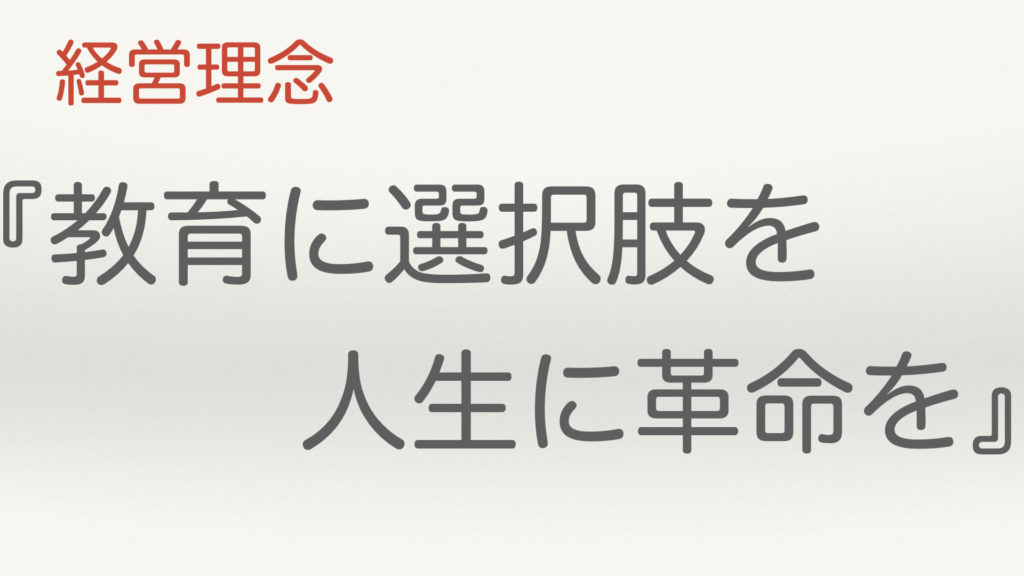
私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。
ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。
さて、今回は、意外と知らない学校の様子に目を向けたいと思います。
本日の内容:【学校の教科書 第1章】意外と知らない学習の評価の在り方
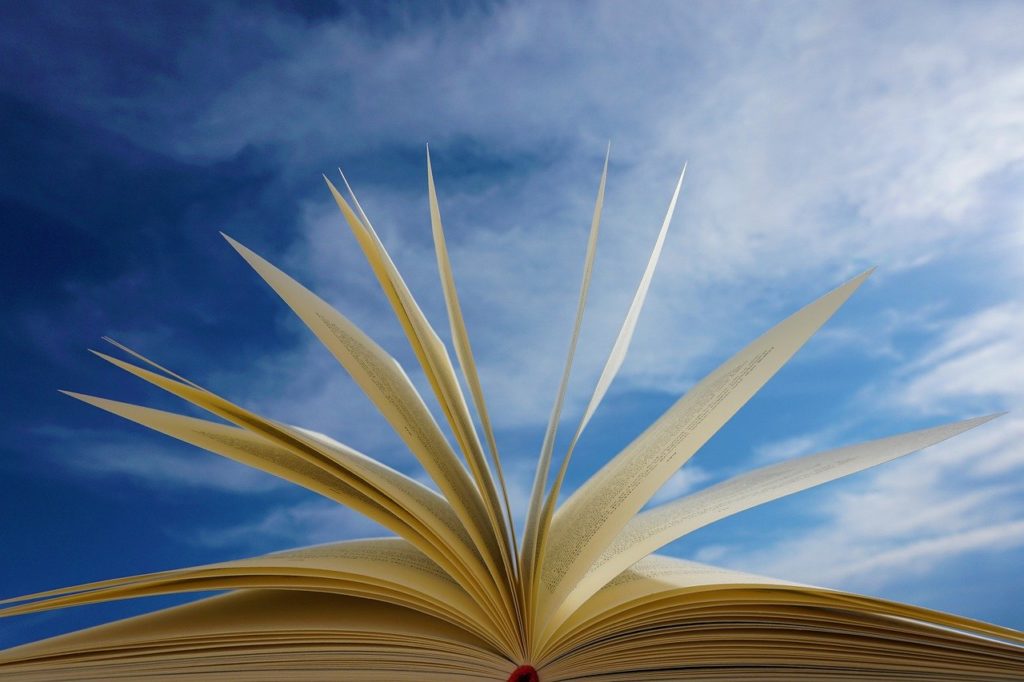
多くの子がより良い学校生活、より良い人生を送ってもらいたい、というのが私の願いです。
そこで、今回から、また新たなシリーズを設けたいと考えました。
そのシリーズとは『学校の教科書』!!
学校=教科書に沿って進む、といった感じなのでなかなかのネーミングセンスだと自負しています(笑)。
学校教育(公共育)で、十分に成果を上げるためのノウハウを教師の立場からお届けしていきたいと思います。
現行の学校教育において、子どもたちが意識すべき大事にすべきポイントをお伝えします。
この教科書に則って学校生活を送っていれば、失敗することはありません。
さて、では、記念すべき『学校の教科書』第1回目の内容は、
学習の評価

『学習の評価』についてお話しさせていただきます。
やはり、学校と言えば”勉強をする所”であるとともに、”勉強の評価を受ける所”であるという意識が強いのではないでしょうか?
それが良いか悪いかという議論もありますが、ここでは、公教育における学校はそういうものであるという前提に立ってお話をさせていただきます。
少し難しい話になりますが、理解をしておくと良い話なので、頑張ってついてきてください。
学習指導要領とは?

学習指導要領というものがあります。
これは、学校教育における目的や目標を示したもので、全ての教科教育は学習指導要領をベースにして行われていきます。
学校の授業は、この学習指導要領をもとに行われています。
よって、先生たちが子どもたちを評価するにあたっても、ここに記載された観点で評価している訳です。
そんな学習指導要領が2020年度の小学校での実施をスタートとして、順次新しくなりました。
この新学習指導要領においては、児童・生徒が学校教育の中で身につけるべき力を、3つの柱で示しています。
それは「個別の知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の3つです。
これに対応する形で、学習状況の評価も行われ、学習状況評価の3観点は「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」となりました。
評価の観点① 知識・技能
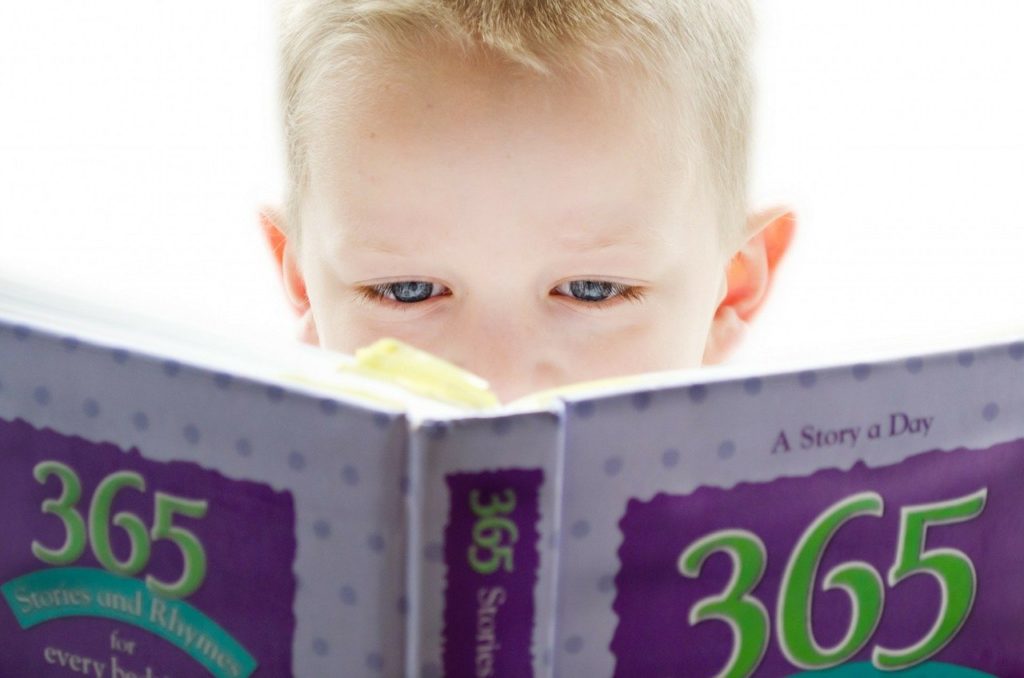
学習評価の3観点のうち、まずは、『知識・技能』という観点について見ていきます。
『知識・技能』の観点では、各教科で身につけるべきとされている知識やスキルについて、十分に習得しているかが評価の対象となります。
ただし、1問1答形式で測るような単純な知識だけではなく、他の教科の知識とも結びつけて活用できるような概念的な知識も重視されます。
そのためペーパーテストにおいても、出題方式が工夫されることになります。
単なる知識を問う問題に加えて、深い理解を試す文章題を使うなど、応用的な部分も含まれることになるでしょう。
この観点は、主にテストの点数や作品の出来栄えで評価されるものと言えるでしょう。
評価の観点② 思考力・表現力・判断力
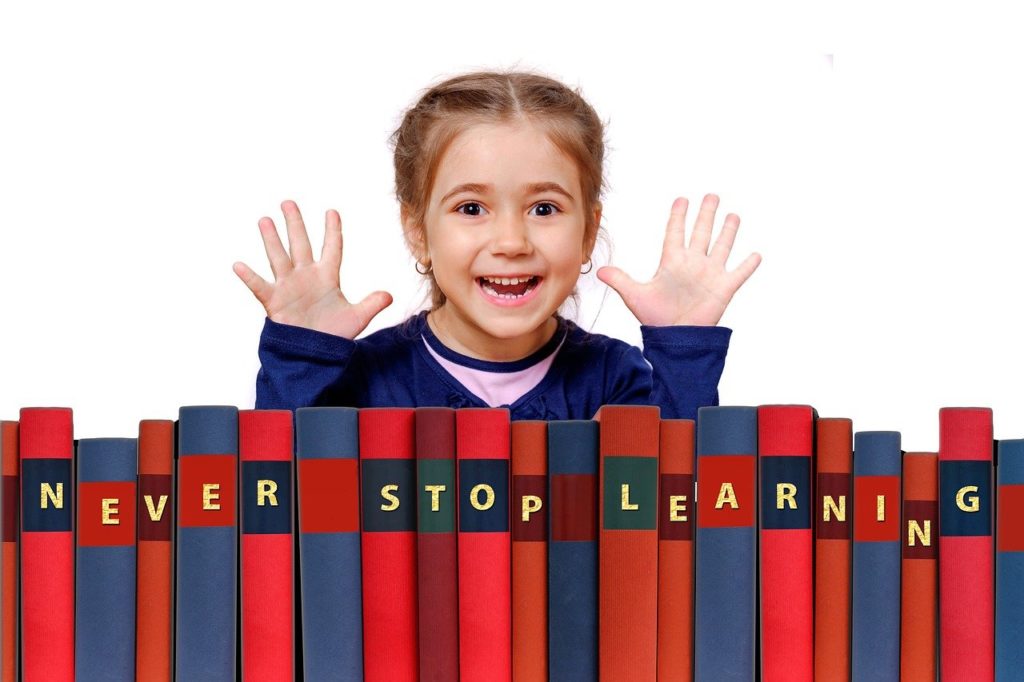
続いては、2つ目の観点「思考力・表現力・判断力」について見ていきましょう。
この観点では、「知識・技能」に比べてより広い力を評価することになります。
各教科教育の中で課題や問題に向き合って解決していく能力や、友達と協力しながら問題解決の糸口を見つけていく力など幅広い能力が評価対象になります。
自らの思いを表現していく能力も評価されます。
こちらの評価については、テストの点数に加え、グループでのディスカッションや発表、レポートなど、具体的な活動の様子や記録によるものとなるでしょう。
テスト以外の部分は、各教科の特性に合わせて評価方法が工夫されていくことになります。
評価の観点③ 主体的に学習に取り組む態度

最後です。3つ目の観点 『主体的に学習に取り組む態度』について見ていきましょう。
これは現在の「関心・意欲・態度」の評価観点に対応するものですが、評価軸はこれまでとは多少違ったものとなります。
これまでの「関心・意欲・態度」においては、どうしてもノートの取り方や挙手の回数など、形式的なものによって判断することが多くなっていました。
「主体的に学習に取り組む態度」においては、さらに深い部分を見ていくことになります。
各教科の内容を理解するために、児童・生徒が「いかに学習を調整して、知識を習得するために試行錯誤しているか」という部分を評価していくのです。
現実的に考えると、この評価は教員の立場からしても非常に難しいものとなります。
おそらくは、これまでのノートの取り方や挙手の回数、提出物の提出状況などによるのが実際になるものと思います。
まとめ

さて、今回は、『学校の教科書第1章 学習の評価』という内容でお話させていただきました。
先ほどもお話しさせていただきましたが、学校において大きなウェイトを占めるのが学習です。
公教育においては、それに伴って評価がついてきます。
この評価については、子どもも保護者も多かれ少なかれ関心事となっているのでは無いでしょうか?
それは、その評価如何では進学に影響したり、子どもの能力を測る目安となったりしているからです。
だとすれば、その評価というものがいかなるものかを最初に知っておくことが大事だと考え、シリーズの第1回目の内容としました。
このことにより、学校生活を送る上で、何をどうやって努力すれば良いのかがわかるようになるはずですが、今回の話はやや専門的でしたので、次回以降に噛み砕いて具体的なアクションプランをお話しさせていただきたいと思います。
新シリーズ『学校の教科書』も、よろしくお願いいたします。
のりそらからは以上です!!
もしこの記事がお役に立てたら下の2つのバナーを1日1回ポチッとクリックお願いいたします!!
それを活力に頑張ります↓↓
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
メルマガもやってます。
リンクを貼っておきます↓↓
そして、これ、便利です。疲れたらドラマでも観て一息つきましょう↓↓

お時間がない方は、Amazon Audibleで↓↓
Amazon Audible(オーディブル)無料体験あり

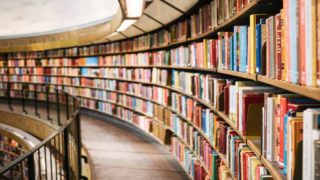








コメント