みなさん、こんにちは。
のりそらです。
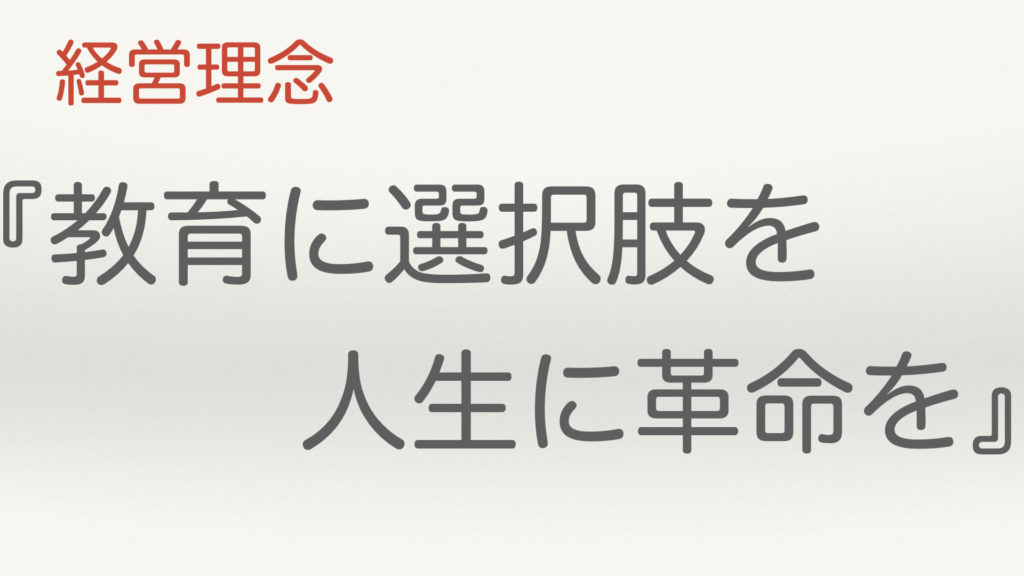
私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。
ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。
さて、今回は、学力についてお話させていただきます。
本日の内容:【教えて、のりそら先生 】13年間連続トップクラス『秋田県の子どもの学力』

題して「【教えて、のりそら先生 】13年間連続トップクラス『秋田県の子どもの学力』」といった内容でお届けします。
今年も文部科学省が「全国学力・学習状況調査」の結果を公表しました。
注目すべきは秋田県。
秋田県は、第1回以来、今年まで13年連続でトップクラスの結果を出しているのです。
小学校・中学校ともに、国語、算数・数学でほぼ上位3番以内に入っています。
秋田県が連続でトップクラスの結果を残している要因はさまざまあるようです。
ここではそのうちのいくつかについて紹介していきます。
今回このお話を聞くことで、秋田県の学力が高い理由の一部について理解することができます。
お子さんの成長に強い関心をおもちの保護者の方々、志をもって子どもたちのために活動しているすべての方々、今何かに一生懸命に挑戦されている方々、教育に関心のあるすべての方々に向けてお話をしていきます。
どうぞお付き合いください。
理由①「探究型授業」が秋田県では一般的に

理由の1つ目として、秋田県内の小学校・中学校で20年以上前から行われている「探究型授業」というのがあります。
探究型授業とは、子ども同士の対話を生かしながら課題を解決していくスタイルの授業です。
秋田県では、国語や算数・数学などをはじめほとんどの教科で、この探究型授業が行われています。
2017年の学習指導要領では「対話的な学び」の授業を進めるべきだという提言がされていますが、探究型授業はその典型的なかたちであり先駆けと言うことができます。
全国学力・学習状況調査では、子ども一人ひとりに児童・生徒質問紙、各学校に学校質問紙が配布され、それに答えるという調査も含まれます。
次の質問をご覧ください。
『学級の友達・生徒との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていますか?』
秋田県は、上記の質問で「当てはまる」と答えた子どもの割合が小・中ともに全国で最も高かったのです。
探究型授業が、スタンダードなものとして県内全域で行われていることの証拠でと言えます。
そのため、秋田の子どもたちは、自ら考えを深め記述して答える設問に強いと言えます。
その証拠として、”全国学力・学習状況調査の記述式設問における秋田県の平均正答率”を見てみます。
小学校 国語 全国平均40.2% 秋田県48.3%
算数 全国平均53.0% 秋田県58.8%
中学校 国語 全国平均56.0% 秋田県60.6%
数学 全国平均35.0% 秋田県38.3%
秋田県は記述式設問での正答率が、全国平均よりもかなり高いことがわかります。
さらに同じ記述式でも、国語では複数の情報を関連させながら答える設問、算数・数学では数式の意味を言葉でわかりやすく説明する設問などで、全国平均をより大きく上回る好結果を出しています。
これはOECD(経済協力開発機構)が2000年に始めた国際学力調査PISA(生徒の学習到達度調査)でも、特に重視されている高次の学力要素なのです。
探究型授業では、学習課題を子どもと先生で決めます。
その後、課題についてまず一人で考え、次にそれをグループで検討します。
その結果を学級に発表して話し合うという過程を繰り返しながら、課題の解決をはかっていきます。
そして、最後に学びを振り返り文章にまとめます。
普段からこのような授業に参加している秋田県の子どもたちは、難しい課題に挑戦することが当たり前となっているのです。
だから、全国学力・学習状況調査の中で難しい設問に当たっても、ひるまずに自分の力で答えを模索しようとするのです。
「探究型授業」の意義、効果、お分かりいただけたでしょうか?
理由②家庭学習を支える取り組み
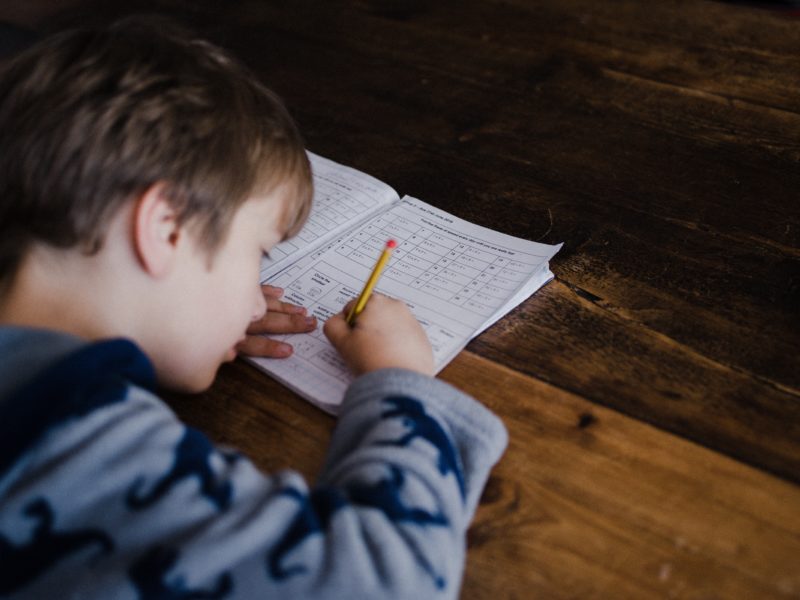
理由の2つ目には、家庭学習を支える取り組みが挙げられます。
秋田県の子どもたちは、家庭学習を充実させています。
それを実現しているのが「家庭学習ノート」の存在です。
まず先生の助言を受けながら、自分で家庭学習の計画を立てます。
その時、復習・予習のほか、自分で発展的に学習したいことも盛り込むようにします。
その計画に基づき「家庭学習ノート」を使って家庭学習を行います。
そのノートを翌日、先生に提出すると、先生は帰りまでにそれを確認して赤ペンでコメントをして返してくれます。
先生の赤ペンを励みに子どもは家庭学習を改善していきます。
つまり、先生が子どもたちに家庭学習の具体的な方法を丁寧に指導することで、家庭学習の習慣化を形作っているのです。
その成果として、秋田県の子どもたちの多くは、自分で計画を立てて家庭学習を進める習慣が身に付いているのです。
理由③子どもたちの学びに向かう姿勢

理由の3つ目は、子どもたちの学びに向かう姿勢です。
秋田県の子どもたちは学習に対してたいへん前向きだと言えます。
そのことを裏付ける質問項目があります。
『◯◯(各教科)の勉強は大切だと思いますか?』
というものです。
国語、算数・数学の勉強を大切だと考える子どもたちの割合は、全国平均に比べて非常に高くなっています。
これには、探究型をスタンダードとする普段の授業のあり方が深く関係している事が考えられます。
課題を自分たちで解決したり、その過程を自分たちの言葉で表現したりする中で、学びの意義を実感するようになっていると考えられます。
また、秋田県の先生は子どもたちをとにかくよく褒めるようです。
『先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思いますか?』
という質問に対しても、全国平均を大きく上回っています。
これらは、子どもたちが先生を強く信頼するということにもつながっています。
そういう環境で育つ子どもたちは、学校の活動に前向きに臨むようになります。
保護者も先生を強く信頼しています。
これらもまた、秋田の学力に大きく影響していると言えるのではないでしょうか。
まとめ

さて、今回は、「【教えて、のりそら先生 】13年間連続トップクラス『秋田県の子どもの学力』」というお話をさせていただきました。
秋田県の学力が高い理由についてまとめてきました。
勘の良い方、これまでのブログを継続的にご覧になっていただけている方々はお気づきかもしれませんが、私たちNEXTAGE SCHOOLはここに挙げた要素を多少のやり方の違いはあれど採用しています。
やはり、行き着く所は同じであると考えることができます。
あとは、どうより良く定着させていくか、アップデートを続けていくか、粘り強く指導していくかなどにかかっていると考えます。
みなさんの学校でも、塾でも、その他教育機関でも参考ししてみてはいかがでしょうか?
私のりそら、日本の、世界の学校の未来がより良いものとなるようこれからも発信していきます。
加えて、これまでのように先生方の日頃の頑張りを世の中に伝えていきたいと思います。
先生方は、どうか日本の子どもたちのために、目の前の子どもたちのために、真っ直ぐにエネルギーをお使いください。
私のできることはさせていただきます!!
のりそらからは以上です!!
もしこの記事がお役に立てたら下の2つのバナーを1日1回ポチッとクリックお願いいたします!!
それを活力に頑張ります↓↓
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
メルマガもやってます。
リンクを貼っておきます↓↓
そして、これ、便利です。疲れたらドラマでも観て一息つきましょう↓↓



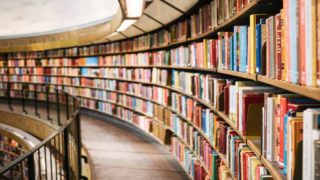




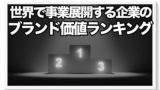
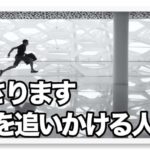

コメント
[…] […]