みなさん、こんにちは。
のりそらです。
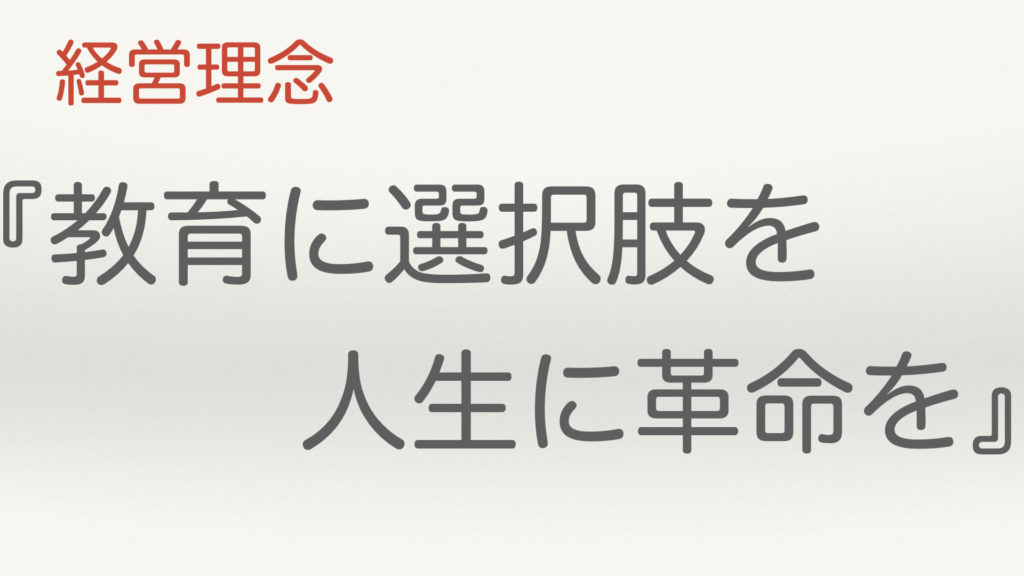
私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。
ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。
さて、今回は、目指す子ども像について考えていきます。
本日の内容:【教えて、のりそら先生 】”何でもしっかりできる子”より”自己表現力が優れた子”
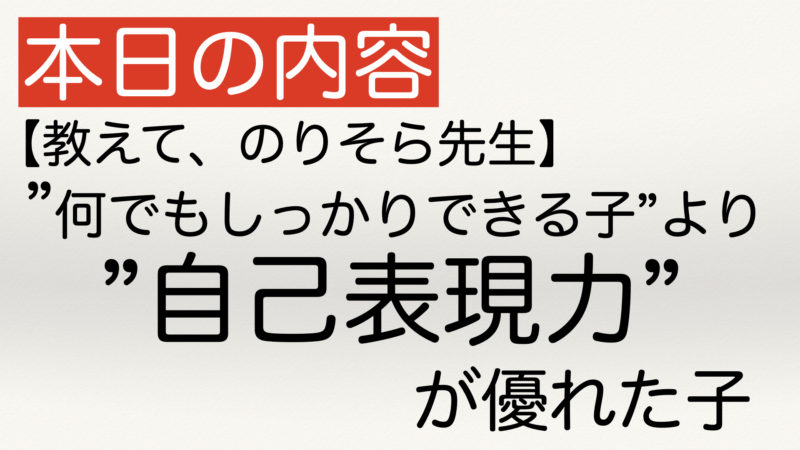
題して「【教えて、のりそら先生 】”何でもしっかりできる子”より”自己表現力が優れた子”」といった内容でお届けします。
みなさんは、子どもたちを、お子さんを、どんな風に育てたいですか?
理想はさまざまありますが、特につけたい力は?
と聞かれたらなんとお答えになるでしょうか?
今回このお話を聞くことで、子どもたちをどのように導き成長させていくことが大切なのかを理解することができます。
学校の先生をはじめ子どもたちの集団を率いる機会がある方々、子どもたちに生きる上で確かな力を育んでいきたいとお考えの方々、教育に関心のあるすべての方々に向けてお話をしていきます。
どうぞお付き合いください。
それでは、いってみましょう!!
結論:目指すは”自己表現力”の育成
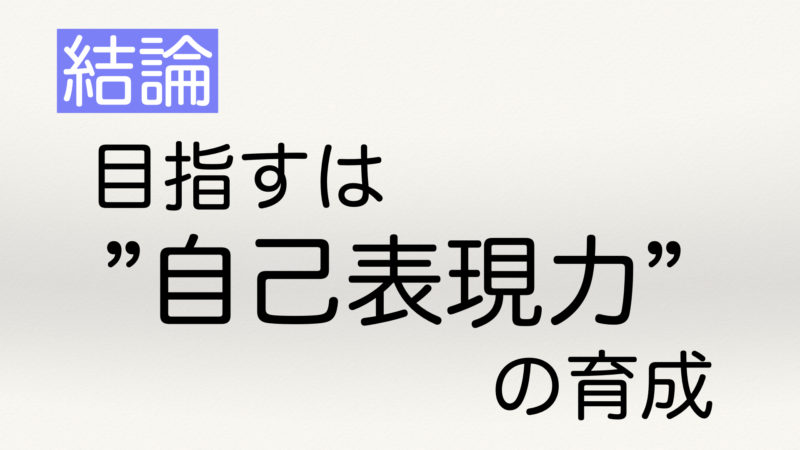
結論です。
目指すは、”自己表現力”の育成です。
”自己表現力”があることで、人は豊かに生きていくことができます。
そう結論づける根拠についてこれからお話していきます。
日本人は表現力に乏しい
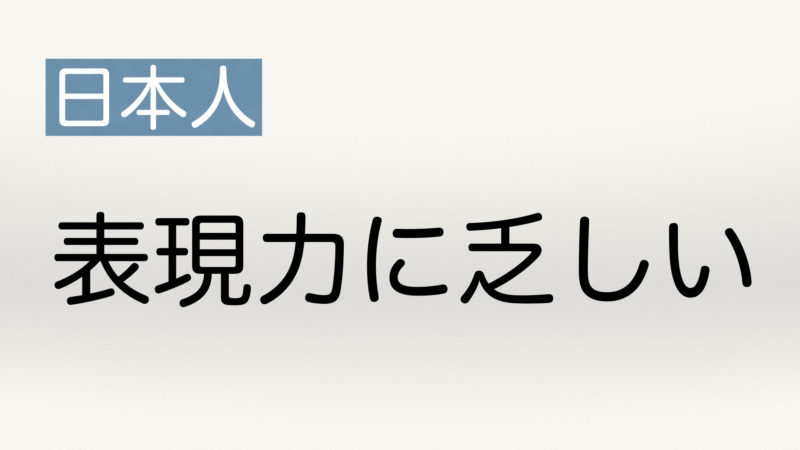
日本人は、「表現力に乏しい」と評価をされることが多い民族です。
これには、もともとの国民性も影響していると見ることができますが、教育によるところも大きいはずであると考えます。
今の日本の教育は、「自己表現力」も含めてさまざまな「自己~」が育ちにくいものとなってしまっているのです。
育ちにくい自己○○
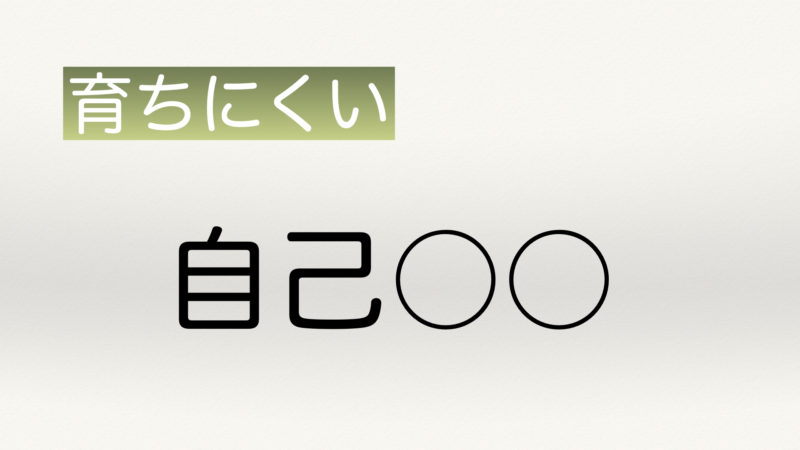
たとえば「自己肯定感」もそのひとつかもしれません。
日本人の自己肯定感は先進国で最低という調査結果が出ています。
いくつかの理由がありますが、子どもたちに「なんでもしっかりできる子がいい子」だというプレッシャーがかかっていることも要因のひとつであると言われています。
親も含めて、多くの大人が暗黙のうちにそういう評価基準を持っていませんか?
そうすると、少しでも失敗すると、子どもは「自分はいい子じゃない」と思ってしまいます。
これでは、自己肯定感が弱くなるのも当然ですよね。
なんだかんだ他人と比べてしまい、なにか劣っていると感じるのもがあると、完璧でないと自覚し、自分はだめだと思ってしまっている、そんな現状です。
誰もが壁にぶつかる
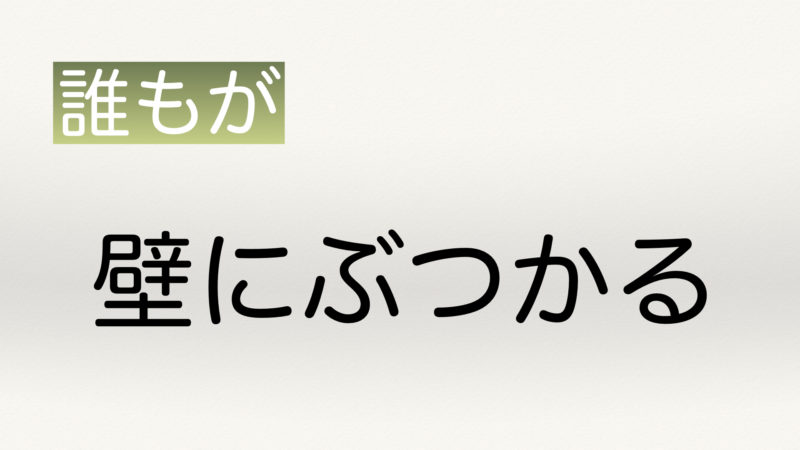
しかし、「何でもしっかりできる子」はどこかで無理をしているものです。
それに、そういうしっかりした子どもであっても、ずっと壁にぶつからないで生きていけるということはあり得ません。
どんな人間であっても、人生のどこかで大きな壁にぶつかるものです。
でも、そのときに「どうすべきか」という手段を知らなかったらどうでしょうか?
立ち上がって再び力強く人生を歩みだすということが難しくなるでしょう。
大事なことは自己分析ができる
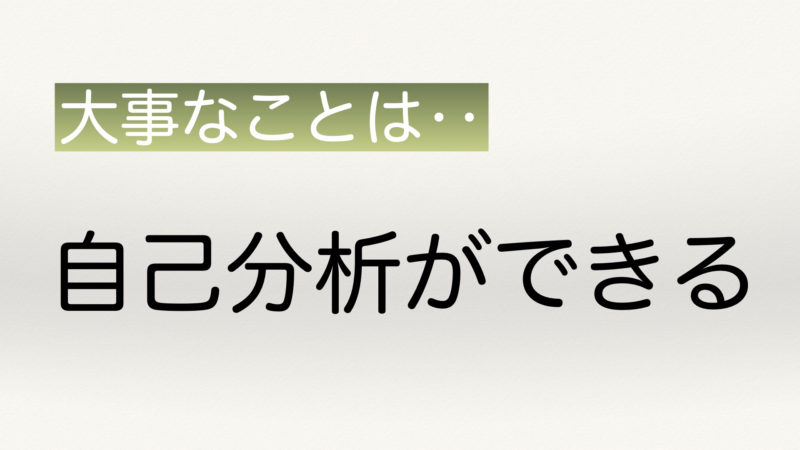
大事なことは、「なんでもしっかりできる子」に育てることではありません。
これには限界がありますし、その過程はハッピーなものではありません。
壁は誰にでも存在するし、それゆえ壁にぶつかってもいいけれど、そのときに大切となるのは、きちんと「自己分析」ができることだと思います。
勉強中にどうしてもわからないことがあったとしましょう。
そのとき、自分の力を測り、区分けし、
「ここまではできるけれど、ここからがわからないから教えてほしい」
と周囲に助けを求められるかどうか。
そこが重要に非常に重要であると考えます。
だから、自己表現力
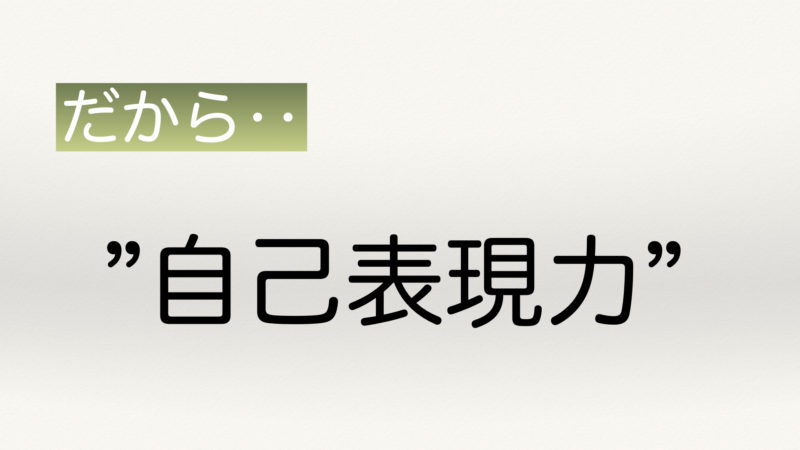
大人だって、ひとりで生きているわけではありませんよね。
誰もがいろいろな人に助けてもらって生きているのが現実です。
「自立」するということは、人の力を借りないことではなく、むしろ、「うまく人に助けてもらう」ことなのです。
そして、そのときに必要とされるのは、自分の置かれた状況を自分の言葉で語って助けを求める、それこそ「自己表現力」です。
この力こそが、子どもたちにつけるべき力です。
提案:もっとコミュニケーションを取りませんか?
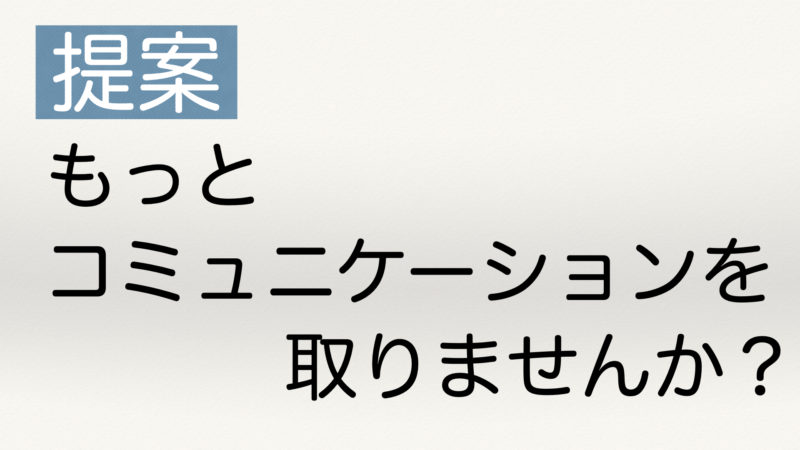
提案です。
自己表現力を伸ばしてあげるためにも、子どものもっとも身近にいる大人である親が子どもとしっかりコミュニケーションを取りませんか?
きちんとコミュンケーションが取れるということは、その時点で良好な関係ができていることでもあり、親子間の「応答性」が育っているということにもなります。
ひとりがしゃべって、もうひとりはずっと黙って聞いている。
こんなものはコミュニケーションでもなんでもありません。
コミュニケーションとは、相互が話して聞く、応答を指すものです。
その応答によって互いを知り、感情を共有したりするなかで、子どもの自己表現力が養われていきます。
考える時間を保証できていない
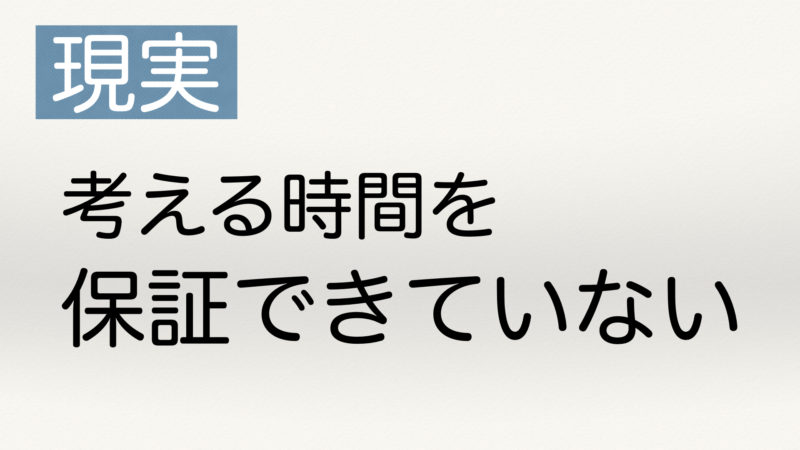
でも、残念ながら、それができていない親御さんも目立ちます。
スーパーで目撃した出来事です。
お母さんが、
「今日は好きなアイスクリームを食べていいから、決めておいてね」
と言って、アイスクリームボックスの前に子どもを置いていきました。
子どもはブツブツとなにやらひとりごとを呟いています。
ちょっとだけ耳を傾けてみると、
「どうしようかな、バニラにしようかな、チョコにしようかな」
と悩んでいるようです。
しばらくして、
「よし、バニラにしよう」
と言いました。
決まったのかと思いきや、今度は
「コーンにしようかな、カップにしようかな」
とまた悩んでいる(笑)。
そして、
「カップはけっこう食べているからコーンにしようかな」
「コーンにしてチョコをトッピングすれば両方食べられるな」
なんてことを言っているところに、お母さんが買い物を終えて戻ってきました。
すると、お母さんが言いました。
「なにやっているの! まだ決まらないの? じゃ、これでいいでしょ」
と。
そんなことでは、今まで子どもが悩みながら考えていたことが一瞬でパーです。
子どもの頭がいちばん働いているのは、悩んで考えているときです。
親は子どもとしっかりコミュニケーションを取って、その考える時間を保証してあげる必要があります。
それが、自分の考えをしっかり表現する力のみならず、「自己選択」して生きているという実感を子どもに持たせることになり、ひいては、自己肯定感を育むことにもなるのです。
ご自身の子どもとの関わりはいかがなものでしょうか?
私は正直‥もっと時間を取ってあげるべきだな、とそう思いました。

私たちNEXTAGE SCHOOLでは、授業の事前と事後にアサインメントと言って、今日やることを子どもたちに話してもらったり、授業を終えてみての感想を話してもらったりしています。
それは、まさに”自己表現力”を育成するためです。
根気のいる作業です。
しかし、きちんと目的意識をもって継続的に取り組まなければ”自己表現力”は育ちません。
目の前の利益に目をやりすぎると、つまりここではサッサと授業に移ろうと思ってしまうと、育たない力となってしまいます。
その大切さをご理解いただきたく思います。
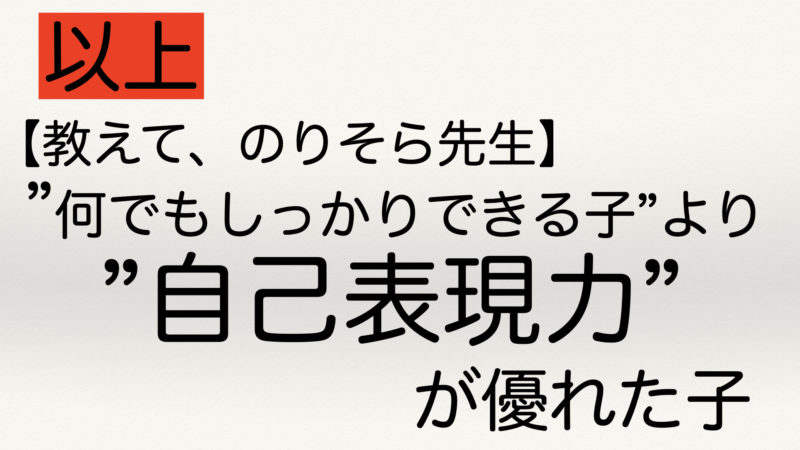
以上、今回の内容「【教えて、のりそら先生 】”何でもしっかりできる子”より”自己表現力が優れた子”」でした。
まとめ

さて、今回は、「【教えて、のりそら先生 】”何でもしっかりできる子”より”自己表現力が優れた子”」というお話をさせていただきました。
冒頭触れましたが、日本人はコミュニケーション力が低いと称されています。
それは、きっと自分で考える機会が少なく育ってきたことが要因として考えられます。
やらされる勉強、やらされるう運動、やらされる~‥これが結局コミュニケーション力の育成を大きく奪っているように感じます。
”自らが考えて、自らが決める経験”によって成功体験を積むことが大切ではなかと思います。
それには、そう導くように指導していかなければならないと思います。
私のりそら、日本の、世界の学校の未来がより良いものとなるようこれからも発信していきます。
加えて、これまでのように先生方の日頃の頑張りを世の中に伝えていきたいと思います。
先生方は、どうか日本の子どもたちのために、目の前の子どもたちのために、真っ直ぐにエネルギーをお使いください。
私のできることはさせていただきます!!
のりそらからは以上です!!
もしこの記事がお役に立てたら下の2つのバナーを1日1回ポチッとクリックお願いいたします!!
それを活力に頑張ります↓↓
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
メルマガもやってます。
リンクを貼っておきます↓↓
そして、これ、便利です。疲れたらドラマでも観て一息つきましょう↓↓



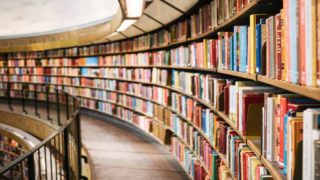





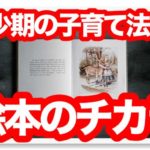

コメント